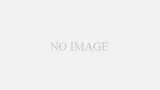住居は生活の基盤となるものであり、離婚することになると、婚姻中に使用した住宅について夫婦の間で整理することが必要になります。
どちらか一方が離婚後にも住宅に住み続けたければ、持ち家ならば、財産分与で所有権を取得したり、所有者となる側と使用契約を結んで住宅の使用を続けることも可能になります。
賃貸住宅であれば、貸主から承諾を得て、賃貸借契約の借主名義を変更することもできます。
こうした離婚するときの住宅の取扱いは、夫婦間で離婚協議書などに記載して確認します。
離婚してからも今までと同じ住宅に住み続けたいのですが、離婚の時にどのようにしたら良いでしょうか?
財産分与によって住宅の権利を得たり、相手から住宅を借りる契約を結ぶことで対応します。相手名義の賃貸住宅であれば、貸主と調整して、借主の名義を相手から自分に変更できることもあります。
住居は生活の基盤となるものですから、離婚後の住居をどう定めるかということは、夫婦双方にとって新しい生活を考えるうえで大切な課題となります。
離婚時の住居に継続して住むことは、夫婦のどちらか一方にしか選択できません。
妻子側が継続して居住したいと望むことが多くのケースで見られます。
何年も暮らし慣れた地域で、近隣の知人らと親しくなっていると、離婚で引越して新たな土地でやり直すことに抵抗を感じるようです。
それとは反対に、夫側は仕事中心の生活を送っていますので、離婚に伴う転居に対してはあまり抵抗感を持ちません。
同じ住居に継続して住み続けることを、妻側が離婚する際の前提条件として提示することは珍しくありません。
離婚する際に住宅の権利について整理することは、離婚時の課題の一つになります。
婚姻中に住んでいた住宅が夫婦の持ち家であるとき、どちら側が住宅の所有権を取得するかということは、財産分与における大事な問題となります。
住宅ローンの支払いが離婚時に残っているときは、離婚後に住宅ローンを負担する側が住宅の所有権を取得することが多く見られる整理方法になります。
住宅に住み続けたい側が住宅の所有権を取得し、さらに住宅ローンも支払っていくことができれば、財産分与としての合意を形成しやすいと言えます。
ただし、整理の方法として、住宅の所有権を取得しない側が住宅ローンの支払いを引き受けることもあります。
こうしたケースは、収入の十分でない妻側に住宅を財産分与として与え、さらに残りの住宅ローンを夫が支払っていくものです。
妻側が子どもの監護をするうえ、収入が多くないときは、このような条件での整理を行うことがあります。
もし、住宅の所有権を取得しない側が離婚後も住み続けるときは、所有者となる相手から住宅を借りる契約を結んでおくことが必要になります。
「当分の間は住んでいても構わない」という曖昧な口約束にしておくと、離婚した後のある日、突然に住宅の使用を許されなくなる事態も起こる心配があります。
離婚した後には双方の生活環境も年月の経過により変化していきますので、離婚する時にはまったく想定していなかった事情が生じることもあります。
そうした事態にも対応できるようにするためには、住宅の使用条件を離婚する時に契約として取り決めておくことが大切になります。
なお、婚姻中に使用していた住宅が賃貸住宅であるとき、継続して住宅に住むことを妻側が希望することもあります。
そのときには、貸主側から承諾を得たうえで、賃貸借契約の借主名義を夫から妻へ変更することで対応します。

離婚の際に住宅の名義をどうするか、どちらが利用するかについて、離婚の条件として定めます。
離婚することになっても、住み慣れてきた環境を変えたくないとの気持ちは理解できます。
もし、離婚する時に賃貸住宅に住んでいれば、自分の収入、離婚後の生活状況に応じて住居を変えることは比較的に容易です。
一方、持ち家に住んでいると、住宅やその環境に対する思い入れが強くあることもあり、そこから離れがたい気持ちにもなります。
持ち家は、家族全員で住むことを前提にしていることから、面積も広く、離婚に伴って居住する人数が減るにもかかわらず住み続けることは、経済効率が良いとは言えません。
つまり、離婚によって世帯が二つに分かれると、住宅ローンの残った住宅をそのまま維持して居住することは、どこかに余分な経済的な負担が生じることになります。
夫婦の共同生活をしていても、住宅ローン負担が家計上で軽くないこともあります。
そうした住宅ローンを離婚してからも継続して負担することは、さらに負担として重くなることが普通です。
離婚する際に夫婦の話し合いによって住宅の取り扱いを決めることはできますが、住宅を維持するために無理をしてしまうと、それが続かない恐れがあります。
割り切った現実的な判断として、離婚する時には住宅を売却する夫婦も多くあります。
住宅に関しての条件を離婚時に取り決めるときには、あまり無理のないように注意しながら、現実味のある整理方法を考えていく意識も大切になります。
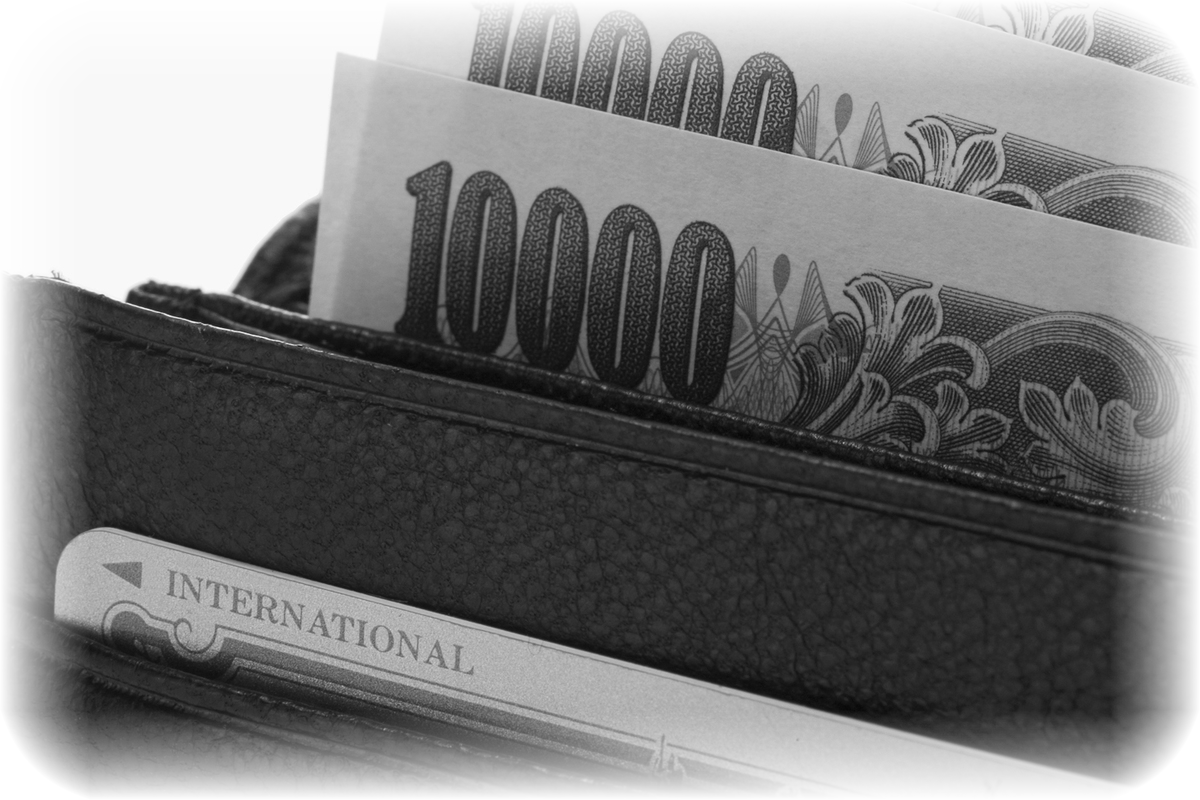
経済的に無理なく、実行できる計画に基づいて離婚の条件を取り決めることが大事になります。
財産分与において夫婦で所有する住宅の整理をするときには、離婚後における住宅の所有権、住宅の使用者、住宅ローンの負担者をポイントとして整理することが大切です。
言い換えますと、住宅は誰のものであり、誰が住んで、誰が住宅ローンを支払っていくかを、明確に整理しておきます。
この辺を明確にしないで「養育費を支払わないから、住宅ローンを支払う」「当分の間は母子が住んで、将来に子どもへ住宅をあげる」などと考える方も見られます。
離婚するときに夫婦である感覚として、将来に困ったときには話し合えば何とかなると考える方もありますが、果たして上手く解決できるかは分かりません。
大事なポイントを曖昧なまま放置しておくと、離婚した後に住宅に関して何か問題が起きたときの対応で双方とも困ることになります。
面倒な面もあるのですが、しっかりとポイントを押さえて整理しておかなければなりません。
離婚時における住宅ローンの整理において、離婚の成立後に住宅ローンを支払う側を、住宅ローンの契約名義人となっていない側に夫婦で変更することもあります。
夫婦の話し合いで離婚後における住宅ローン負担者を変更しても、そのことで住宅ローンを貸している銀行は、住宅ローンの契約を簡単に変更してくれるとは限りません。
あらたに住宅ローンを返済する者に十分な収入が無ければ、契約名義の変更は認めません。
仮に収入が十分であって変更することが可能になるときも、住宅名義を合わせて変更したり、必要となる変更手続きを銀行は求めてきます。
また、銀行からの承諾を得ることなく住宅ローンの負担者を変更することもありますが、そうしたときは返済に遅れが生じると、契約上の債務者に返済を求めることになります。
住宅ローンの負担者を変更することは、夫婦間の問題として整理するほか、貸し手になる銀行との関係においても整理が必要になります。
離婚する際における住宅の扱いは、離婚した後の生活に深く関わります。
住宅は財産評価額が高く、住宅ローンのあるときには負担が重いものになります。
そのため、住宅の整理は離婚の条件でも中心となり、夫婦での話し合いが必要になります。
例えば、離婚した後に住宅を売却して代金を二人で配分するときには、売却の方法、配分額を離婚する際に取り決めておきます。
また、住宅ローンの支払いを契約上の債務者とは違う側が行なっていくとき、又、財産分与による所有者名義を変更する時期が将来になるときは、取り決めを契約書に作成しておくことが必要になると考えます。
そして、住宅以外の財産分与、慰謝料の支払いなど、夫婦間で確認した事項すべてについて、離婚協議書又は公正証書に整理しておくことが離婚する手続きとして大事になります。
こうした夫婦間の約束を公正証書に作成しておく必要があるか否かについてご質問をいただくこともありますが、それは取り決める内容によって判断することになります。
何でも公正証書に作成する義務はありませんが、離婚後にも長く支払い等が続いたり、金額が大きくなる契約では、公正証書 離婚により手続をすすめることが望ましいと考えます。
婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用になられたい方は、お問い合わせください。
「メール」または「電話」だけによるサポートにも対応していますので、全国どちらからもご利用になれます。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。

『あなたに必要となっている公正証書、離婚協議書、示談書などを迅速・丁寧に作成します。』