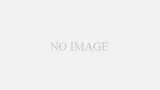離婚において財産分与の対象となる財産は、婚姻生活した期間に夫婦で形成したものです。
したがって、結婚する前から存在する預貯金などの財産または別居した後に作られた財産は、その形成に夫婦による協力がないことから財産分与の対象財産になりません。
こうした夫婦の共同財産に当たらない財産を「特有財産」と言います。
結婚前から貯めていた銀行預金をもっているのですが、離婚するときは、こうした預金も財産分与として相手と分けなければなりませんか?
財産分与の対象は、夫婦が共同生活のなかで一緒に築き上げてきた財産になります。結婚する前からある預金は、あなたの努力だけで貯めたものですから、財産分与として相手に分ける必要はありません。
婚姻生活のなかで夫婦で共同して築き上げてきた財産は、離婚の時に財産分与として夫婦で分けて清算をします。
預貯金、自動車、不動産など、どちら側の名義になっている財産であっても、婚姻期間中にできた財産は、夫婦の共同財産として財産分与の対象になります。
住宅を購入するときは一般に住宅ローンを利用しますが、このような婚姻生活のためにできたローン債務も、財産分与のなかで清算するマイナス財産になります。
マイナス財産も、プラス財産と合わせて財産分与のなかで清算します。
ただし、婚姻生活に起因しない借金は財産分与の清算対象にはなりません。
また、子ども名義の預貯金でも、その原資が夫婦の共同財産から出ていれば、実質的に夫婦の共同財産になります。
夫婦の関係を解消するときは、こうした共同財産を夫婦で分けて清算します。
財産分与では、夫婦の話し合いで配分の割合を自由に決めることができます。
一般に、夫婦で平等に半分ずつに分けることを基本(2分の1ルール)としながら、多少の調整を加えながら双方で納得できる財産分与を定めます。
財産分与では、存在する財産を分ける限り、対象財産の評価が上昇していないときは所得税、贈与税は課されません。
都市部の不動産については評価額が当初から上昇していることもありますので、財産分与では注意が要ります。
なお、夫婦の一方が結婚する前から有していた財産、婚姻期間に取得した財産でも贈与又は相続を原因として取得した財産は、どちらも財産分与の対象になりません。
これらを特有財産と言いますが、夫婦の協力に関係なくできた財産であるものです。
そのため、あなたが結婚する前から貯めていた預金は、離婚するか否かに関わりなく当然にそのままあなたの財産となります。
相手から財産分与の請求を受けても支払う義務はありませんので、心配いりません。
以上のことは財産分与の基本的な考え方になりますが、初めて離婚の手続きをすすめるなかであなたのように心配する方は多くあります。
なお、婚姻前の預貯金を婚姻中に購入する住宅資金に充てることもあります。
住宅は夫婦の共同財産になりますで、住宅を評価するときに自分で持ち出した資金を別枠にして財産分与と区分して清算します。
ただし、住宅の評価額が大きく下がっていたり、住宅ローンの残債務の額が住宅の評価額より大幅に上回っているときは、実質的な回収が困難になることもあります。
婚姻期間に形成された財産であっても、夫婦が別居している期間に増えた財産は、原則として財産分与の対象になりません。
夫婦で共同生活をしていないため、両者の協力のもとに形成された財産とは見られません。
そのため、別居をしている夫婦が離婚に向けて財産分与の話し合いをするときは、別居を開始した時点における財産を基準にして財産分与を考えます。
なお、対象財産を別居開始時としても、財産分与における財産評価の時点は離婚時になるものと考えられます。
また、別居期間には、夫婦の間で生活費の分担金として婚姻費用が支払われます。
しかし、別居になった経緯などから婚姻費用が支払われていないこともあり、そうしたときは離婚時に財産分与のなかで合わせて清算することもあります。
精算金の支払い契約をするときには、離婚 公正証書などに定めておきます。
別居中にできた財産は、財産分与の対象から除外されます。
実家が資産家である相手と離婚をするとき、いずれ相手が相続で得られる財産があることを、離婚時の財産分与で期待する方もあります。
婚姻を続けるならば、いずれ相手が相続を受けることになり、そして相手が先に亡くなれば、その配偶者の立場にあるあなたが財産の多くを相続する権利者となります。
しかし、離婚時点で相手が所有していない財産は相手に処分権はありませんし、離婚の成立によって配偶者としての相続権はすべて失われます。
なお、配偶者としての相続権が失われることは仕方ありませんが、夫婦に子どもがあれば、その子どもは相続権を引き続き持ちます。
父母の離婚によっても、子どもは親子関係に変更を受けないためです。
なお、婚姻中に相手が相続により財産を取得したとしても、相続を原因として取得した財産は特有財産となり、財産分与の対象となりません。
したがって、結論から言えば、相手の実家の財産は財産分与に関係しないことになります。
このような財産分与上の仕組みを意外に勘違いしている方も多くあるようです。
第762条(夫婦間における財産の帰属)
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
婚姻前と婚姻後における財産の両方が、一緒になっている財産も存在します。
その典型例として、婚姻中に夫婦が住宅を購入するときに、一方又は双方が婚姻前に貯めていた預貯金を頭金として住宅の購入資金に充当するケースがあります。
また、一方の親から贈与を受けた資金を充当することもあります。
こうしたときは、離婚時における住宅の評価額を共同財産と特有財産に按分して分けることで財産分与をすすめます。
この様な整理方法は、生命保険を対象として、離婚時の解約返戻金から財産分与の金額を算出するときにも適用することがあります。
婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用になられたい方は、お問い合わせください。
「メール」または「電話」だけによるサポートにも対応していますので、全国どちらからもご利用になれます。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。

『あなたに必要となっている公正証書、離婚協議書、示談書などを迅速・丁寧に作成します。』