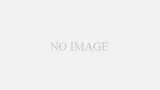自分だけでは十分な収入を持たないけれども離婚したいと思ったときは、離婚した後の生活に不安を抱きます。
共同生活を解消して別々の生活へ移行しても双方が経済的に自立して生活できることを事前に確認しておくことは、離婚の最終判断をする際に欠かせません。
とくに、子どもを監護しながら生活することになる側は、自分で子どもを監護養育できるかについて慎重に検討しておかなければなりません。
いったん離婚が成立したならば、元の生活へ引き返すことはできなくなります。
私はパートで仕事をしているため、毎月の収入が10万円位しかありません。離婚する約束として、夫から養育費を月額5万円受け取る予定ですが、それでも離婚後の生活に不安をもちます。どうしたら良いでしょうか?
毎月15万円の収入で生活が成り立つか、十分に確認しておきます。それで大丈夫であれば、離婚後の生活をスタートできます。また、不測の事態にも備えて、離婚後の経済生活をできるだけ小さくすることが求められます。もし、離婚後の生活が成り立たない見通しであれば、自立できる収入を得られる仕事につく準備をしてから離婚することを考えることも現実的な対応になります。
結婚または出産したことを契機としていったん仕事を辞めた妻は、子どもが幼いうちはパート勤務などで仕事に就いているケースが多くの家庭で見られます。
なかには、完全に仕事を辞めてしまって主婦業に専念することもあります。
このような家庭の夫婦が離婚することになると、妻側は、自分の収入が少ないため、離婚した後の経済生活に不安を抱くことになります。
婚姻期間が短いときの離婚では財産分与の対象財産も僅かとなり、婚姻期間が長いときも住宅ローンを返済中であると、ほとんど金融資産を持たない家庭もあります。
それでも、離婚した後は、それぞれ自分の収入で生活していかなければなりません。
十分な財産分与を受けることなく離婚することになる妻は、収入も少ないことから、離婚した後の生活に不安を持ちます。
また、幼い子どもを監護しながら仕事をして生活しなければならないと、その面でも負担が重くなることから、妻側の不安は大きくなります。
そうした生活への不安があるときは、両親から支援を受けることを考えるとともに、離婚してからの生活を小さくすることが求められます。
妻側の収入が少ないケースでは、養育費の額を水準額よりも少し高目に設定したり、離婚後の一定期間は生活の補助を目的として夫側から定期金を給付することを離婚の条件にすることもあります。
一方で、妻の側としては、できるだけ生活を安定させるため、児童扶養手当など公的扶助の受給条件を離婚前に市区役所で確認しておきます。
ただし、夫側の収入が高くないときには、養育費の額も低くなります。
また、しばらくの期間は養育費を受領することができても、子どもが成人したり、学校を卒業することで、養育費は終了します。
このようなことから、離婚後には妻側の経済的な自立が求められます。
離婚しても自立して生活できることが分れば、離婚したいときは、多少は苦しくとも離婚することも選択できます。
もし、自分の収入と養育費などの離婚給付だけでは自立して生活できる見込みがなければ、離婚する時期を先に延ばし、まずは自立できるだけの収入を得ることができる仕事に就くことを考えなければなりません。
自立して生活できるだけの収入を得られるようになってから離婚することも考えられます。
収入が少なくて離婚後の生活に不安のある妻側が親権者となって子どもを監護養育することになるときは、養育費の支払い条件が重要になります。
養育費は家庭裁判所で利用される「算定表」を参考にして決めることもできますが、子どもを監護する親の事情に合わせて夫婦の間で自由に養育費の条件を決めることもできます。
はじめから離婚した後の経済生活が厳しいことが見込まれるのであれば、少しでも不安を軽減できるような養育費の条件とするように夫婦で話し合いをしてみます。
子どもを監護する親としては、話し合いに多少の時間がかかることになっても、離婚後に子どもと生活できる水準で養育費を定めることが必要になります。
また、夫婦の共同財産に住宅のあるときは、財産分与で妻に住宅を取得させたり、夫が住宅を取得する場合でも、子どもが独立できるまでの間は、妻と子に無償で住宅を使用させる条件を定めることもできます。
そうした財産分与に関する重要な確認をしたときは、公正証書 離婚を利用します。
離婚後の生活スタートに大きく影響する離婚の条件になりますので、離婚の届出までに、生活設計を踏まえてしっかり定めておくことが大事になります。
夫婦に共同財産がないときには、普通であれば、財産分与はないと考えます。
でも、財産分与、慰謝料の支払いが何も無ければ、離婚時に手持ち資金がまったくなくなり、給与収入も少ない妻としては離婚することに現実に応じられなくなります。
また、幼い子どもを連れて離婚することになると、母子の経済生活は困窮します。
こうしたときは、夫側は財産分与で対応することも考えます。
財産分与は、離婚時の夫婦の共同財産を清算するだけでなく、離婚後の生活資金の給付を対象とすることもあり、これを扶養的財産分与と言います。
熟年離婚では、扶養的財産分与として、離婚してから妻が年金受給を開始するまでの間、定期金を支払う約束がされることもよく見られます。
幼い子どもがあるときにも、離婚後における母子の生活状況を考えて、夫から経済支援を受けることを離婚条件として考える必要のあるケースもあります。
金銭を支払うことに抵抗があれば、妻に対して住宅の無償使用を認めたり、賃貸住宅の賃料を夫側が負担するなどの生活支援を離婚する条件とする方法もあります。
このように、財産分与は離婚するときに調整できる条件として利用される面もあります。
子どものある離婚では、養育費の取り決めが重要になります。
離婚後に子どもを監護養育する親側の収入全体に占める養育費のウェートが高くなると、養育費の支払いが滞ってくる事態になると、直ちに生活に重大な支障が生じてきます。
そのため、子どもを監護養育する親側にとっては、養育費をしっかりと確保することは経済生活の基盤を安定させる上でたいへんに重要なことになります。
安定的に養育費が支払われ続けるためには、何よりも養育費を支払う側の経済力が十分にあることが前提になります。
そして、継続的な支払いをすることができる養育費の支払い条件とすることが必要です。
養育費を負担することになる親が、離婚したいために収入に見合わないまでの高い養育費を約束することも見られますが、そうした無理な約束を長く続けられることはありません。
養育費の条件を取り決めるときは、夫婦で十分に話し合っておくことが大切になります。
また、養育費の支払いが万一滞納したときに備えて、公正証書を利用して養育費の支払いを契約として定めておくことも、支払い確保のうえで有効な方法になります。
公正証書の作成には若干の期間が余計にかかりますが、その代わり、契約した養育費の支払いが滞納したときには裁判をしなくても財産差し押えの手続きが可能になります。
このため、養育費のほかに財産分与や慰謝料の支払いがあるときにも公正証書 離婚の手続きが利用されています。
離婚が成立すると、夫婦はそれぞれ単独で生計を維持していくことになります。
また、子どもを監護する側は、生計を維持するだけでなく、子どもへの教育も合わせて行なわなければなりません。
離婚によって父母の共同監護体制はなくなりますので、監護する親の責任は重くなります。
そうしたことから、自分の病気、怪我、失業など不測の事態に備えて、できるだけ普段から生活の規模を小さくしておくことを求められます。
さらに、世帯主として、万一の事態に備えて生命保険を利用することも考えられます。
離婚したことで生活水準を下げたくないと考える方も多くありますが、そのためには収入の裏付けがなければなりません。
離婚した後には、できるだけ収入に見合った生活水準に近づけていくことが理想となります。
婚姻中と変わらない生活を続けていくのではなく、生活における支出を見直すことで支出の抑制に努めながら、万一のときに備えて少しずつでも貯金を増やしていきます。
もちろん、生活に対する価値観には個人差がありますので、実際には自分で納得できる範囲内で対応していくことになります。
人生で困ったときに相談できる相手として、両親はいつでも心強い存在になります。
もし、両親が健在であるときは、離婚に際して両親に相談をしておくことも必要になります。
離婚した後に妻が子どもと一緒に両親と生活をすることは、一般にも多く見られることです。
離婚して経済的に厳しい生活状況になるとき、毎月の住居費の負担が無くなることは生活するうえでたいへん楽になります。
また、離婚に伴って転居するときも、転居先が馴染みのある地域であると生活しやすいです。
両親と共同生活をすることで、互いに困ったときにたすけ合うこともできますので、子どもを育てるうえでも安心できます。
もちろん、両親へ迷惑を掛けたくないとの気持ちを持つことも理解できますが、子どもが厳しい状況にあるときは、そのことを両親も心配することになります。
一緒に生活をすることで、両親も安心できることになる面もあります。
婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用になられたい方は、お問い合わせください。
「メール」または「電話」だけによるサポートにも対応していますので、全国どちらからもご利用になれます。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。

『あなたに必要となっている公正証書、離婚協議書、示談書などを迅速・丁寧に作成します。』