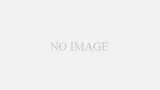離婚を原因として支払われる慰謝料、養育費は、原則として課税対象になりません。
慰謝料は、損害賠償金であり、支払いで利益を受けるものではありません。また、養育費は、扶養義務に基づく生活資金の支払いになります。
ただし、支払われる額が社会通念から過大であると課税当局から認められると、その超える金額分に対して贈与税が課されることもあります。
通常の離婚契約では、養育費、慰謝料の支払いに対し課税を受けることはありません。
ただし、例外的な離婚給付契約を結ぶケースもありますので、そのようなときには税務署、税理士などに事前にご相談ください。
養育費は、離婚に伴って非監護者となる親から、監護者親(一般に親権者と同じ)に対して、子どもの衣食住などの生活費、医療教育の費用についての分担金として支払われるものになります。
このような法律上の扶養義務に基づいて支払われる養育費は、課税される対象になりません。
課税された後の自分の生活費を被扶養者の生活費に配分するため、その給付が目的通りに使われていれば、課税の必要はないと考えられます。
ただし、一括払いの養育費に関しては、支払う金額がその時点において必要な限度を超えるものとみなされて、贈与税の課税を受ける可能性のあることには注意が必要になります。
離婚の慰謝料は、有責配偶者から他方配偶者に支払われる精神的苦痛を償うための損害賠償金になりますので、非課税として取り扱われます。
しかし、慰謝料の金額が一般的基準と照らし合わせて余りにも高額であるというような場合、超える金額について贈与税が課税されることもありますので、注意が必要になります。
課税を受ける心配がある高額な離婚給付について当事者間で合意をする場合には、あらかじめ税理士に確認をしておかれるとよいでしょう。
以上のように、離婚のときに支払われる養育費、慰謝料については、基本的には課税対象にならないと考えてよいでしょう。
なお、財産分与についても、基本的には夫婦の共有財産を清算する手続きであるとして贈与とはみなされないため、課税はされません。
ただし、過大な給付のある財産分与と認められると、超過した分について贈与税が課されることも考えられます。(財産分与の税金)
また、財産分与で住宅(土地、建物)の分与を行なうときには、特に注意が必要になります。
住宅を取得した際の価額よりも財産分与時における評価額が高くなっているときは、その差額となる増加額について譲渡所得があったものとして課税されることがあります。
このような可能性のあるときには、税理士などに事前に確認しておき、課税される税金も踏まえた財産分与を行なうことが必要になります。
夫婦の子どもが扶養控除対象になるときは、収入の多い側で扶養控除対象にしています。
離婚をした後は、どちらか一方しか扶養控除を受けることができなくなり、扶養から子どもを外すと控除枠が減りますので、そのぶん税金は高くなります。
また、婚姻中にパート勤務をしている妻を扶養対象にしている場合、離婚に伴って上記と同様に税金制度における控除枠が変更されることに注意が必要になります。
なお、税金の制度に関する詳しいことは、勤務先の給与担当者、最寄りの税務署までご確認をお願いします。
〔扶養控除の概要:国税庁HPから抜粋(平成30年)〕
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族(扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)となる人がいる場合は一定の金額の所得控除が受けられ、これを扶養控除といいます。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(※1) | 38万円 | |
| 特定扶養親族(※2) | 63万円 | |
| 老人扶養親族(※3) | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等(※4) | 58万円 |
※1 「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
※2 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。
※3 老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
※4 同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
※5 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
税金については、簡単な法律書をひも解くことだけでは整理することができません。
やはり、課税主体となる税務署に心配なことを確認することが安全であり、それを聞きずらい事情のあるときは税理士に相談をすることが安心であると言えます。
行政書士や弁護士は税金に関する実務を扱っていませんので、大まかな仕組みに関すること以外には詳しい回答をすることはできません。
やはり、専門的な事項については、その道の専門家に確認することが間違いありません。
離婚に原因のある側は、相手に対して離婚に伴う慰謝料を支払うことになります。
このとき、離婚原因が不貞行為であるときは、有責配偶者のほかに、その不貞相手も例外を除き慰謝料の支払い義務を負うことになります。
こうしたときに不貞相手から慰謝料を受け取るとき、それが正当な権利行使としての損害賠償金であることを当事者の間で確認をしておくために示談書が作成されます。
示談書を作成しておかないと、高額な慰謝料を受領したときに、その金銭が何を原因として受領したものであるかを課税当局に資料により説明することができません。
当事務所では、示談書のほか、不倫 慰謝料の請求書(不倫 内容証明)の作成も扱ってます。もし、示談書の作成などが必要でしたら、ご照会ください。
「離婚協議書の作成でしたらお任せください。」
財産の移動が起きるときには税金のかかることがあります。
ただし、離婚における財産分与、慰謝料、養育費の各給付については、基本的に税金が課されません。
不動産のような高額な財産の移動に限らず、離婚を原因とした金銭の移動があるときは、離婚協議書を作成しておくと、税金面にかかる説明に対応することに役に立ちます。
夫婦の間での金銭の移動が何を根拠にして行われたかについて、いつでも書面で説明することができるからです。
離婚協議書では、財産分与、慰謝料、養育費など、各項目ごとに離婚に関する条件を記載することになります。
そのため、離婚に伴い支払われる金銭の根拠を、それぞれについて確認をすることができます。
当事務所の離婚相談では離婚協議書、夫婦の合意書の作成について対応をしておりますが、税金は対象外となります。
婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用になられたい方は、お問い合わせください。
「メール」または「電話」だけによるサポートにも対応していますので、全国どちらからもご利用になれます。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。

『あなたに必要となっている公正証書、離婚協議書、示談書などを迅速・丁寧に作成します。』