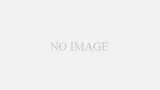離婚するときには、未成年の子どもについて父母の一方を親権者に指定する必要があります。
親権者の指定は、離婚の届出時に限り、父母の合意だけで可能になります。
離婚の成立後に親権者を変更したいときは、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。家庭裁判所の関与なく、父母の協議だけで親権者を変更することは認められません。

協議離婚する際には夫婦の話し合いにより、夫婦の間に生まれた未成年の子すべてについて、父母のどちらか一方を親権者に指定して離婚届に記載します。
市区町村役所への協議離婚届では、子どもの親権者の指定を必要的な記載項目としています。
そのため、子どもの親権者の指定をしていない離婚の届出は受理をされません。
離婚の成立後、父母双方の事情が変わったことなどを理由に離婚届出のときに定めた親権者を変更することも可能になります。
ただし、離婚届出時とは異なり、離婚の成立後に親権者を変更するときは、父母間の話し合いだけは認められていません。
子どもの親権者を変更したい側は、相手親の住所地(合意で定めることも可能です)の家庭裁判所に親権者変更の調停又は審判を申し立てることが必要になります。
家庭裁判所では、親権者を変更することが子どもの福祉に適うことになるかという観点から、親権者の変更を認めるべきか否かについて検討します。
新たに親権者となる親に、子の教育をする意欲、能力、環境が備わっているかどうか、また、子の成長の状況や子本人の意見を聴いたうえで、親権者の変更を判断します。
子どもが幼いうちであれば、母親が親権者として優先される可能性が高くなります。
離婚した後で親権者を途中で変更することは、子に重大な影響を及ぼすことになりますので「子の利益に適うことであるか」という観点から判断されます。
なお、親権者を変更する回数に制限はありません。
民法第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2~5 省略
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
若い夫婦だけに限らず、離婚後に再婚する可能性は高くあり、実際にも多くの方が離婚した後に再婚しています。
再婚することで新たに家庭を築いていくことは、離婚した後にも長く続く人生を豊かにするうえで意義あることであると思います。
なお、未成年の子どもを監護する親権者が再婚すると、再婚に伴って新しい配偶者と子どもを養子縁組することが一般に見られます。
養子縁組の成立により、父母の共同親権の下で子どもは監護養育されることになります。
再婚があると、離婚時などに決めていた養育費又は面会交流の条件見直しも、実父母にとって整理すべき課題になります。
まずは実父母の間で話し合って、条件の変更について決めることになります。
再婚に伴う条件の見直しは、非親権者の親が再婚したときも必要になることがあります。
もし、実父母の間で条件の見直しを決められないときは、家庭裁判所に調停を申し立てます。
子どもの監護者を指定したり変更することは、離婚の前後に関わりなく、父母間で合意できれば家庭裁判所で調停することは不要です。
ただし、父母間の協議によっては監護者の変更について合意が成立しないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることになります。
監護者は父母以外に祖父母が就く事例もあります。
なお、関係者の間で合意ができる限り、家庭裁判所が関与しなければならない仕組みにはなっていません。
また、子どもの監護者は、戸籍に記載される仕組みもありません。
離婚する際に子どもの親権者を指定するものの、離婚した後に親権者を変更する場合の条件を離婚 公正証書に定めておきたいという希望を持っている方が少なからずあります。
その理由は、離婚時には相手を子どもの親権者に指定することに同意するけれども、相手を完全に信頼できないことから、将来に親権者を変更する可能性について含みを残しておきたいと考えることからです。
親権者となる母親が不貞行為をしていた事実のある離婚では、父親は、母親が子どもを監護することに不安を抱くことがあります。
しかし、親権者を変更するためには、上記のとおり、家庭裁判所で調停又は審判の手続きを経ることが手続上で必要になっています。
そのため、仮に父母間で将来の親権者変更について条件を定めておいても効力は生じません。
また、そうした法律上で無効となる契約を公正証書に記載することはできません。
記載する場合にも、変更について協議する旨の合意にとどまると思われます。
このようなことから、離婚の届出時に親権者を指定するときには、父母双方が納得できるように十分に話し合いを重ねたうえで指定しておくことが大切になります。
離婚の届出時に指定した親権者が離婚の成立後に死亡した場合、生存している他方の親が自動的に親権者になる仕組みにはなっていません。
親権者を失った子どもについて、子どもの法定代理人となる未成年後見人を指定することが、原則は行われる仕組みとなっています。
ただし、未成年後見人の指定が行なわれる一方で、生存している他方の親から、家庭裁判所に親権者の変更について申し立てされることも想定されます。
この場合、家庭裁判所では、子どもの福祉の観点から、親権者の変更について審判がされることになります。
新たに親権者を指定することは子どもの福祉面で重大な影響を及ぼすことから、生存している他方の親を親権者に指定するか否かについて判断されます。
離婚の成立に伴い親権者となった親は、子どもが成年になる前に自分が死亡した場合に備えて遺言により未成年後見人を指定しておくことができます。
未成年後見人は、親権者に代わり、未成年者の法定代理人になります。
遺言で未成年後見人を定めておくと、親権者が死亡すると直ちに未成年後見人に就きます。
そうしたことから、他方の親に親権者になって欲しくないときには、子どもに相応しい未成年後見人を考えて、自分が死亡した時に未成年後見人に就任してもらうことを遺言によって措置しておくことがあります。
なお、未成年後見人に就いたときは、10日以内に市区町村役所へ未成年後見人の届出を行わなければなりません。
民法第839条(未成年後見人の指定)
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。
民法第840条(未成年後見人の選任)
前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。
2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
3 未成年後見人を選任するには、未成年後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
民法第841条(父母による未成年後見人の選任の請求)
父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなkればならない。
はじめての協議離婚の手続に不安のあるとき、離婚専門の行政書士による離婚契約書の作成支援サービスなどをご利用いただくことができます。
当事務所では、離婚協議書、公正証書離婚など、協議離婚契約をメインとして、夫婦や男女に起きる問題を解決するときに必要となる契約書を作成しています。
離婚契約書(離婚協議書・公正証書 離婚)、夫婦の合意書、不倫の発覚時における慰謝料 示談書、不倫 慰謝料、婚約破棄に伴う慰謝料の請求書(不倫 内容証明)などを、ご依頼を受けた内容を踏まえて、ご相談しながら作成します。
これまでに多くの夫婦の離婚相談、離婚契約書の作成により培ってきたノウハウを生かして、ご依頼者様のご要望に対応させていただきます。
ご利用の方法はメール・電話だけでも可能であり、全国どちらからでもご利用いただけます。

遺言を利用して、死後における未成年後見人を指定できます。
離婚後に親権者となった親は、自分の死亡したときに備えて未成年後見人を遺言により指定することができます。
もし、親権者である自分が死亡しても、他方の親に親権者になって欲しくないときには、未成年後見人を遺言により指定しておくと、死亡後の遺言執行者による届け出により未成年後見人が子の法定代理人となって、子の監護などを行うことになります。
離婚になった経緯から、父母間の信頼関係が完全に壊れてしまっているような場合、万一のときに他方の親が親権者になることを回避するため、上記のように未成年後見人の指定を遺言によって行なっておくことも考えられます。
ただし、他方の親から、親権者の死後、親権者指定の審判の申し立てが行なわれることもありますので、このことには注意しておく必要があります。
未成年後見人の指定に関する遺言書の作成をお考えでありましたら、サポート対応もさせていただけます。
婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したいとお考えであれば、お気軽にお問い合わせください。
ご来所のほか、メール又はお電話によるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、ご利用者の方からの連絡等に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

『あなたに必要な公正証書、示談書を迅速・丁寧に作成します。』
こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
047-407-0991