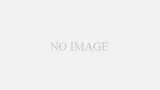不倫が原因で離婚することになると、夫婦で話し合って慰謝料の支払いについて定めます。
その際には不倫相手から支払われる慰謝料額に影響を受けますが、不倫をした配偶者は、自分の不倫相手へ慰謝料を請求されることを回避させたいと考える傾向が見られます。
そうしたとき、自分ですべての慰謝料を負担することを条件として不倫相手に対しては慰謝料請求しないことを夫婦の間で合意することがあります。
もし、不倫した男女の一方による支払い額によって慰謝料の全部が満たされると、理論上では不倫相手に対する慰謝料の請求はなくなります。
不倫相手に慰謝料の支払いを求めずに不倫問題を解決することもあります。
離婚の原因が夫婦の一方による不倫(不貞行為)であるときは、夫婦による協議離婚にかかる条件協議で離婚慰謝料の支払い条件が定められることになります。
慰謝料の支払い条件を取り決める際には、不倫で被害を受けた配偶者に対して不倫相手から支払われる慰謝料の額が影響します。
その理由は、不倫は法律上では男女二人による共同不法行為にあたり、不倫した男女二人が被害者に対して慰謝料の支払い義務を負う(不真正連帯債務)ことになるからです。
そのため、被害者は、不倫した男女の両方又は一方に対し慰謝料を請求することができます。
そして、離婚協議における夫婦の合意として、不倫した配偶者が慰謝料すべてを支払うことを条件とし、不倫相手に慰謝料を請求しない約束をすることもあります。
また、不倫の事実が発覚した場合にも夫婦で離婚しない選択をし、その後に婚姻生活を継続させるなかで夫婦関係の修復を目指すこともあります。
このようなときに夫婦間で合意書が交わされることがあり、このなかで不倫相手に対しては慰謝料を請求しない確認を行うこともあります。
不倫 慰謝料は、不倫した男女2人に負担する義務があることは上記の説明とおりです。
ただし、慰謝料を請求する側は、男女のどちらか一方又は両方に請求することを選べます。
また、両方に慰謝料を請求するときは、それぞれに請求する慰謝料の額を決められます。
ただし、両方から受領できる慰謝料の合計額は、慰謝料の全体額が上限となります。
つまり、一方だけに慰謝料請求するときに比べて、両方に対して慰謝料請求するときは合計で二倍の額になるという訳ではありません。
慰謝料として受け取ることが認められる合計額を、それぞれに振り分けるに過ぎません。
なお、離婚をしないときは、配偶者に対し慰謝料を請求しても家計としての収支上では意味を持ちませんので、現実には不倫相手だけに慰謝料請求することが行われています。
このような慰謝料請求の仕方は、不倫に関する一義的な責任は不倫した配偶者にあるという考え方からすると問題視されることもあります。
ただし、慰謝料請求の実務として、不倫相手だけに慰謝料を請求することは行なわれており、その請求をすることに法律上で問題はありません。
離婚に向けた夫婦の話し合いでは「不倫相手に対しては慰謝料を請求しない」という合意を行うこともあります。
その理由として、不倫した配偶者の側が不倫相手に対して迷惑を掛けたくないとの意向から、自分で慰謝料すべてを負担して支払うということがあります。
このとき、その慰謝料の額が被害者側の請求できる額をすべて満たしている額であるかどうかがポイントとなります。
不倫した配偶者が慰謝料の全体額を満たす慰謝料を支払えば、そのことにより不倫相手に追加して慰謝料請求できる余地はなくなります。
一方、配偶者から支払われる慰謝料の額が慰謝料の全体額を満たしていなければ、不倫相手に対しても、足りない慰謝料の差額分を請求できます。
夫婦の間で不請求に合意したにも関わらず不倫相手に慰謝料請求することは、合意違反になりますが、それを行うこと自体は法律上で有効になります。
ただし、慰謝料請求する側が不倫相手に対して慰謝料を免除する意思表示をしていたときは、慰謝料請求することは認められないという考え方もあります。
夫婦の間における合意として不倫相手に慰謝料請求しないとしておきながら、その一方で不倫相手に慰謝料を請求することは合意違反になります。
ただし、慰謝料請求すること自体は可能になり、そして慰謝料請求を受けた側から慰謝料が支払われることもあります。
もし、夫婦間の合意に違反して慰謝料が請求されて慰謝料を受領したときは、夫婦間の合意に違反したことを理由として損害賠償請求が起きることもあります。
不倫相手に慰謝料請求しないことを求めるのは、もっぱら男性に見られることです。
不倫問題における慰謝料の仕組み上では男女の区別はありませんし、男女での考え方に一律に違いがあるとは言えません。
しかし、不倫問題の現実における対応においては、男女それぞれの立場、事情又は考え方が反映されることが起きます。
不倫相手に慰謝料請求しないことを配偶者に対して求めることも、その一つになります。
女性よりも男性の方が経済力の備わっていることが一般に多いことから、弱い立場にある不倫相手の女性を庇う気持ちが不倫問題の対応において現われることになるのかもしれません。
不倫が原因となる離婚では、不倫による被害を受けた配偶者側は、不倫した男女二人に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料を請求する側としては、離婚する時に受領できる金銭をできるだけ最大化するために、どのように離婚の条件を組むことがベストになるのかを考えます。
離婚した後の生活不安を軽減させるために、少しでも多くの資金を得ておきたいからです。
そのようなとき、離婚に伴って受領できる慰謝料は一般には高額となりますので、できるだけ安全な一時金によって少しでも多くの金額を受け取りたいと考えるものです。
そのため、慰謝料請求できる相手二人の資力などの状況を見ながら、慰謝料請求する配分などについて決めることになります。
不倫に関する慰謝料の請求権があっても、その行使方法において悩む方も多くあります。
不倫が原因となる離婚での慰謝料額の取り決めについては、上記のように、夫婦だけではなく不倫相手も関係します。
そのため、夫婦で慰謝料の支払い条件を話し合うときには、その点にも注意を払います。
慰謝料を受領する側としては、不倫した当事者二人に対して不倫 慰謝料の額をどのように配分するかを考えながら慰謝料の支払い条件を決めようとします。
不倫を原因とした離婚において配偶者へ慰謝料を支払ったことから、もう自分の不倫相手には慰謝料請求がないだろうと思っていたところ、離婚して1年ほど経ってから元配偶者が不倫相手に対し慰謝料を請求したことに驚いて、ご相談されてきた方もあります。
不倫に伴う慰謝料は発覚から3年間は請求権が残りますので、このようなことが現実に起きて不思議はありません。
夫婦で離婚の条件を決めるときは、公正証書を利用することも考えたうえで、慰謝料を含めて双方で十分に確認しておくことが大切です。
不倫相手に対しては慰謝料を請求しないとの合意が夫婦の間にできたのであれば、そのことも離婚契約書に記載しておくことができます。
不倫の問題を解決するためには、夫婦間の関係、不倫をされた側と配偶者の不倫相手の関係の両方について整理することになります。
不倫することは法律上で共同不法行為にあたることから、夫婦だけの問題ではなく、不倫相手も関係者に含めて対応します。
まずは、二つの関係に分けて対応の方法などを検討することになります。
夫婦間では、離婚することになれば離婚協議書(離婚公正証書)を作成し、離婚しないときは誓約書(二度と不倫をしないことなど)を作成することを検討します。
一方、慰謝料を請求する側と不倫相手は、慰謝料請求(不倫 内容証明)して双方間に合意が成立するときは慰謝料 示談書を作成して不倫 慰謝料の支払い条件を確認します。
配偶者に不倫された側は、不倫問題に関する法律上の仕組みを踏まえながら、不倫問題の解決に向けて忙しく動くことになります。
夫婦の間に不倫問題が起きても、直ちには離婚しない方向で解決を図ることは多くあります。
夫婦の一方が不倫などの過ちを犯しても、それを夫婦で乗り越えて、夫婦の関係を再構築していこうとする考え方になります。
このとき、配偶者の不倫相手だけに対し慰謝料請求することもあります。
また、婚姻関係を継続させることを優先するため、不倫相手に慰謝料請求しないでおき、夫婦間だけで不倫問題を早期に決着させることもあります。
ただし、この場合、婚姻を継続する際に不倫が再発することは重大な障害となりますので、被害者となった側は、不倫相手から「二度と配偶者に接触しない」との誓約を取り付けたいと考えます。
このとき、誓約書の提出を求められた不倫相手は、それで不倫問題の一切が解決するのならと考えて、誓約書を差し出すこともあります。
しかし、こうした手続きには落とし穴があります。
誓約書の作成時に不倫の慰謝料について整理しておかなければ、不貞行為による慰謝料請求権の消滅時効(3年間)が成立するまでは慰謝料請求が起きる可能性を残します。
つまり、不倫問題は完全に解決していない状態で続くことを知っておかなければなりません。
とくに誓約書を出す側としては、対応において十分な注意を払います。
言われたとおりに誓約書を出したにもかかわらず、そのあと忘れた頃になったある日突然に、過去の不倫に関する慰謝料請求書が送られてくることもあります。
このようなことを防止するためには、要求された誓約書を直ちに差し出すのではなく、双方で確認事項について示談書として作成し、取り交わしておくことが必要になります。
誓約書を相手から取り付ける側も、将来にトラブルの余地を残すような方法で対応してよいかどうかを検討しなければなりません。
時間の経過と共に人の気持ちは移り変わっていくものであり、このことは不倫問題の話し合いにおいても見られます。
「あなたから慰謝料を受け取るつもりはありません」と言われたのに、その後に慰謝料の請求書が送付されてきたという相談を受けることも少なからずあります。
しかし、単なる口約束のままであったときには、言った言わないのという水掛け論になってしまうため、当事者の間での最終的な合意内容を確認することができません。
このようなことから、不倫の解決に関して当事者の間で合意したことを確認する場合は、示談書を作成することが重要になります。
いったん当事者の間で示談が成立すれば、余程の特別な事情がない限り、示談した条件を後で撤回することは認められません。
もし、示談の撤回が容易に認められることになれば、権利関係が不安定になってしまいます。このように、示談は重要な法律上の行為となります。
「不倫対応に実績がありますので安心してご利用になれます。」特定行政書士
日本カウンセリング学会正会員
不倫の問題が起きたときには、一般に被害者側が主導して問題の解決を図ることになります。
加害者の側から動くことも可能ではありますが、下手に動くことで相手を余計に刺激してしまうことになりかねませんので、行動には自制が求められます。
こうしたとき、被害者の側から、まずは不倫関係を解消する旨の誓約書を出して欲しいと言われることがあります。
当事務所ご利用者の方は、加害者側のこともあれば、被害者側のこともありますが、どちら側からのご依頼についても、当事務所では示談書を作成して解決することをご提案します。
しかし、加害者側からのご相談を受けていますと、被害者側から先に誓約書の提出だけを求められているとのお話をお聞きすることがあります。
このような差し入れの誓約書が問題解決にならないことは上記にご説明のとおりです。
どうして、このようなかたちでの誓約書を求められるようになるのか不思議ですが、そのような手続きを第三者から勧められることもあるようです。
そのような請求を受けた側は、誓約書を渡すことは仕方ないことであると誤解していることもあり、後になって問題になってしまうことになります。
不倫のトラブルに対応するときには、慌てて場当たり的に対処するのではなく、対応手続きを慎重に検討しながら適切な対応をすすめていくことが大切になります。
婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用になられたい方は、お問い合わせください。
「メール」または「電話」だけによるサポートにも対応していますので、全国どちらからもご利用になれます。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。

『あなたに必要となっている公正証書、離婚協議書、示談書などを迅速・丁寧に作成します。』