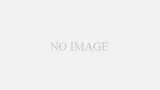親権者は、子どもの法定代理人として、その財産を管理し、身分にかかる行為を代理します。
協議離婚の届出時には父母のどちらか一方を子どもの親権者に指定しますが、監護者を親権者とは別に定めることも認められます。
なお、離婚した後に親権者を変更するには、家庭裁判所の調停又は審判の手続きを経ることが必要になりますが、監護者の変更は、父母の協議だけでも行なうことができます。
未成年の子の監護者が、父母ではなく祖父母になることもあります。
夫婦の間に未成年の子どもがある協議離婚では、離婚の届出に際して、父母のどちらか一方を離婚後における子どもの親権者として指定することが必須の手続きになっています。
親権には、子どもの「財産管理権」と「身上監護権」があります。
そして、親権と監護権は、原則として一体であることが想定されています。
ただし、離婚時における家族の状況によっては、父母の判断によって、親権から監護権を切り離して定めることがあります。
典型な例としては、離婚時に父母間で子の親権の指定に争いがあって、子に関する権利を父母で分けて持てるようにと、親権者と監護権者を分離することに合意することがあります。
父母の一方を親権者とし、他方を監護権者にすることは、父母間の話し合いで自由に定めることができます。
このように、親権と監護権を分けて定めることを「分属」といいます。
家庭裁判所の実務では原則として分属を定めず、あくまでも例外的に認められることがあるというのが実情になります。
子に対する権利を離婚後に父母の間で分け合うことは、将来的に子どもに対する教育方針等の違いが父母間で表面化したときなどにトラブルが起こることも心配されるからです。
このため、離婚時に夫婦が深刻な対立状況にあって、離婚後に意思疎通をすることが見込まれないような場合では親権者と監護権者を分けることは良くないと考えられます。
法律が離婚後に父母の一方を親権者に指定するように定めている主旨からも、親権と監護権は一体的に運用することが基本であり、子どものためにも安定すると考えられています。
監護権は、離婚届の届出事項になっておらず、その変更も父母間で行なうことができます。
一方の親権は、協議離婚届において夫婦の一方を指定し、離婚後の親権者変更には家庭裁判所の手続が必要になります。
このように、監護権と親権では、変更するときの取り扱いが異なります。
離婚するときにおける父母と子どもの状況は、それぞれの家庭ごとに異なります。
父母のどちらか一方で子どもを監護していくことが基本になりますが、なかには離婚によって父母のどちらも子どもを育てることが難しい環境におかれることも考えられます。
このときには、父母以外の者を監護権者として定めておくことができます。
まず考えられるのが、父母の両親、すなわち子どもからすると祖父母です。祖父母であると、子育ての経験があり、血のつながっている子に対する深い愛情もあることから安心できます。
監護権者の指定という形式的な手続きをしなくとも、事実上で祖父母が子(孫)の面倒を見ているケースはあります。
もし、監護権者について父母間で話し合いが着かないときには、どちらか一方が家庭裁判所に対して監護権者の指定について申し立てをすることができます。
父母のどちらか一方が監護権者となるよりも、祖父母がなる方が子の福祉に適するとの判断となれば、祖父母でも子の監護権者になることができます。
監護権者は子に対する監護教育を担うという重要な責任を持ちますので、何よりも子どものためにとって良い選択であるかどうかがポイントになります。
夫婦が離婚に至る事情は様々ですし、それぞれのケースで複雑な事情のある離婚もあります。
離婚時の夫婦間協議において、子どもの親権者の指定が円滑に決まらないこともあります。
そして、その結果として、親権者と監護権者を夫婦(父母)で分けることもあり、監護権者を父母以外に定めることもあります。
このとき、父母側の事情を考慮することもやむを得ないことになりますが、親権者・監護権者は子どもにとって大きな影響を与える事項になりますので、子どもの福祉の観点から望ましい形として親権者・監護権者の指定をすることが重要になります。
協議離婚するときには、養育費や財産分与などの離婚条件について夫婦で取り決めたことを、公正証書なども利用して、離婚契約書に定めることが行なわれています。
親権者と監護者についても、離婚契約書に他の条件と合わせて定めることになります。
親権者の指定は、協議離婚の届出における必要項目となり、戸籍にも記載される事項になりますが、監護者については戸籍への記載も行なわれません。
それは、通常では親権者と監護者が同一になることが想定されているためです。
そのため、両者を分けて定めるときには、夫婦で取り決めたことを契約書で確認しておくしかなく、とくに重要になります。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前2項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前3項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ。
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用になられたい方は、お問い合わせください。
「メール」または「電話」だけによるサポートにも対応していますので、全国どちらからもご利用になれます。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡やりとりに支障が生じますので、ご遠慮ねがいます。
『あなたに必要となっている公正証書、離婚協議書、示談書などを迅速・丁寧に作成します。』