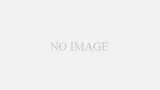婚姻中は夫婦による共同親権になりますが、離婚する際には夫婦の一方側を親権者に指定することが必要になります。親権者は同時に監護者を兼ねることが原則的な形になりますが、夫婦の話し合いで合意ができれば、一方が親権者となり、他方が監護者となることもできます。
親権は、子の利益のために、子の監護や教育をしたり、その財産を管理する権利となります。この親権を行使できる者を、親権者と言います。
子が未成年である間は、子が単独で法律上の行為をすることに制限を受けますので、親権者が子の法定代理人となり、子の利益が損なわれないように守ります。
たとえば、日用品以外の高額な物品を購入する契約をしたり、学校などにおける各手続きをする際には、親権者の承諾が必要になるのです。
夫婦である期間中は、夫婦が共に親権者となり、共同して親権を行使することになります。
ところが、夫婦が離婚するときは、父母の一方側を親権者に指定することが必要になります。
そのため、夫婦の間に未成年の子があるときの協議離婚では、父母の一方側を親権者に指定したうえで、協議離婚の届出をしなければなりません。
日本の制度では、離婚後は父母のどちらか一方だけに親権が付与されることになることから、親権者の指定について父母間で意見が合わずに、親権をめぐって争いになることがあります。
親権者の指定は離婚するうえでの必要条件であるとことから、もし親権者が決まらなければ、離婚を成立させることができません。
多くの夫婦は協議離婚を選択するため、夫婦の話し合いで親権者を決めることになります。
夫婦の話し合いをもって親権者が決まらないときは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。
まだ子が幼いうちであると、特別の事情がなければ、多くのケースにおいて母親が親権者に指定されており、その割合は8割近くにもなります。
家庭裁判所が関与して子の親権者を決めるときの視点としては、子の福祉(健やかな成長)のために、父母のどちらが適切であるのか、というところになります。
家庭裁判所で判断するときの基準としては、次のものがあります。
- 【継続性】現在、子の面倒を見ている側の親に継続させる。
- 【子の意思】子自身の考えも尊重する。
- 【母親優先】幼い子であれば、母親が適当である。
- 【兄弟姉妹の不分離】特に小さな子であると、兄弟は一緒の方が良い。
親権者の指定は子の側にとって極めて重要なことになりますので、家庭裁判所では子自身の意思も確認しながら、専門調査官による調査をすることもあります。
協議離婚をお考えになられているときは、上記の基準も参考にして、子の利益を考えて最適な判断をすることが必要になります。
親権者と監護者
離婚後には父母の共同親権ではなくなります。親権者の指定は、離婚届のときに必要な事項になります。
第818条(親権者)
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行なう。ただし、父母の一方が親権を行なうことができないときは、他の一方が行なう。
第819条(離婚又は認知の場合の親権者)
父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
協議離婚では、夫婦で話し合って、すべての子について、どちらか一方を親権者に定めます。
このとき、親権者を将来に見直しすることを条件として付けようとすることが見られますが、そのような親権に条件や期限を付けることは認められません。
また、離婚後に親権者を変更するためには、家庭裁判所の調停、審判の手続きを経ることが定められています。つまり、親権者の変更には必ず家庭裁判所が関与することになるのです。
このように、離婚するときには夫婦の話し合いだけにより親権者を指定できますが、離婚後には夫婦の都合だけで親権者を変更することは認められないこともでてきます。
なお、離婚時における夫婦間の話し合いで、条件の協議を有利に進めるために自らが親権者となることを主張することも見受けられるようです。
しかし、そのような行為は、子の利益にならないことになりますので慎むようにしなければなりません。親権者以外の条件で、話し合うべきことになります。
どちらが親権者となることが子のためになるのか、そのような観点から親権者を考えます。
離婚の条件として自らが親権者となることを相手側から同意を得るために、離婚後の養育費を受け取る権利を放棄することを離婚時の夫婦間の話し合いで約束することがあります。
若い夫婦だけに限らないことですが、傾向として、離婚を急ぐ若い夫婦で、子どもが本当に幼いときに見られることが多いと言えます。
養育費を受け取らない旨の夫婦間での合意は有効になりますので、そのような取り決めをすること自体には問題はありません。
ただし、本当にそのような条件で離婚後に支障なく子どもを監護養育していくことができるのかを十分に考えたうえで、慎重に判断をしなければなりません。
赤ん坊であるうちは監護養育にそれ程にお金がかかりませんが、段々と子どもが成長するにしたがって、どうしてもお金が必要になってきます。
若く人生経験も少ないと、将来の人生設計に具体的なイメージが湧かないこともありますし、何とかなるだろうと考えてしまうこともあるかもしれません。
離婚後に養育費を請求したいとのご相談を受けることがありますが、そのような方には、昼間は社員として仕事をし、夜間には複数のアルバイトをこなしているようなこともあります。
離婚後に再婚をする方が多いことは事実なのですが、必ずしも再婚するとは限りませんし、また再婚をしても再び離婚することもあります。
離婚を急いでいるときには、周りの状況が見えなくなってしまうこともないとは言えません。
そうしたときに大切なことを見落とさないように、ご両親に離婚することを事前に報告し、心配なことを相談するなどして、気持ちを落ち着けてから進めていくことをお勧めします。
協議離婚のとき、夫婦(父母)間の話し合いで親権者を指定することになりますが、このとき、親権者だけを指定することが通常です。
ただし、例外的なケースとして、親権者とは別に監護権者を定めることがあります。
監護権は、親権の一部であり、親権から、財産管理と身分行為についての代理権を除外したものであり、子の監護や教育をする権利になります。
そのため、日常的な生活の範囲内においては、監護権があれば、子と一緒に暮らしていくことができると言えます。
一般には、親権と監護権を分けて定めることはありませんが、夫婦の事情や考え方によって、夫婦(父母)で離婚後の親権者と監護権者を分けます。
なお、家庭裁判所では、親権と監護権を分離すること(これを「分属」といいます)を好ましいものと考えていません。
親権者を父母のどちらか一方にするという法律上の原則に反することになりますし、現実の生活においても、監護権者だけでは子に関する対応ができない事態も生じることも起きます。
また、親権者と監護権者の意見が相違することがあれば、子の監護において悪い影響が出ることも考えられます。
ただし、父母間で役割分担が上手く機能することになれば、悪い面ばかりでもないと言えますので、最終的には父母間で慎重に協議したうえで決めることが大切になります。
監護権者は、父母間の協議で決めることができ、変更することもできます。
ただし、父母間での話し合いで監護権者の指定について問題が起きたときには、家庭裁判所の調停、審判で監護権者について定めることになります。
このとき、子が15歳以上のときは、家庭裁判所は子の意見も聞くことになります。
親権者と監護権者を分けて定めたときは、その条件を夫婦が話し合って決めたケースになります。そのことからすれば、夫婦(父母)間での話し合いはできる状況にあると言えます。
ただし、夫婦が離婚したことからすれば、夫婦(父母)間には何らかの価値観、意見の相違があったことが離婚の背景にあると考えられます。
そのため、離婚後に子どものことで監護権者だけで手続ができないとき、親権者の了解を得なければならない場面もでてくることがあります。
そのときには父母間での話し合いが必要になりますが、円滑に整理して決めることできないリスクがあると言えます。
そうしたことも踏まえて、親権者と監護権者を分けることを決めることになります。

『離婚のときの取決めは離婚協議書、公正証書にしておきましょう。』
子どもの親権者・監護権者の取り決めは、夫婦で定めることになる離婚条件の基本事項のひとつになります。
親権者を指定していないと、役所に協議離婚届を提出することもできません。
夫婦が離婚するときは、親権・監護権者のほかにも、養育費、面会交流、財産分与などの定めておくべき事項があります。
このような夫婦で約束する重要なことは、離婚後になってトラブルとならないように離婚協議書に記して残しておくことが大切になります。
離婚協議書は個人の方にも作成できますが、法律面の知識不足、理解の仕方、誤りなどから、正確な記載が難しいと言えます。
なお、養育費、財産分与の分割金などの金銭支払いが離婚後にも残るときには、公正証書 離婚も利用されています。
いろいろなことを相談しながら、希望に合わせた離婚協議書を作成したいという方には、専門家を利用することも一法です。
それまで疑問に思っていたこと、知らなかったこと、間違って理解していたことなどが解けることによって、安心して、希望する内容で離婚協議書、公正証書を作成することができます。
離婚契約の専門行政書士事務所として、離婚契約書の完成までを丁寧にサポートさせていたくプランをご用意しています。
婚姻費用、公正証書離婚、婚約破棄・不倫の慰謝料、示談書など各サポートのお問合せはこちらへ
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書などの各サポートをご利用することをお考えのときは、ご相談ください。
ご来所でのほか、メール又はお電話によるお問合せにも対応します。
慰謝料請求の可否・金額に関する判断、離婚手続・不倫対応の方法を確認するだけのお電話は、ご利用者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

『あなたに合わせた公正証書、示談書などを丁寧に作成します。』