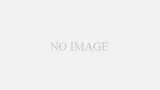聞き慣れない「公正証書」とは、どのような手続で作成させることができ、それを公証役場で受け取れるのか、初めての方であると分からず戸惑うこともあります。
協議離婚で作成する公正証書は、養育費など、夫婦で決めた離婚の条件を整理した契約書であり、夫婦である二人が公証役場へ出向いて公正証書の原本に署名と押印をして、公証人手数料の支払いと引き換えに公正証書の正本又は謄本を受け取ります。
なお、事前に公証役場へ公正証書の作成を申し込むときは、どちらか一方だけでも手続ができることが普通であり、最後の公正証書による契約手続は夫婦二人で公証役場へ出向きます。
離婚の届出前に公正証書を作成する予定なのですが、夫婦二人で公証役場へ行くことになりますか?
夫婦の意思を確認したうえで公正証書を作成しますので、公正証書を完成させる契約手続には当事者となる夫婦二人が公証役場へ行くことになります。なお、公証人が認めた場合に限り、本人が指定した代理人で公証役場の手続きを代行することもできます。
公正証書とは、権利と義務などについて公証人が作成する証書のことです。
協議離婚で公正証書が利用される場面としては、協議離婚するにあたり夫婦で養育費や財産分与などについて取り決められ、それを契約書に作成するときです。
離婚する条件を定める契約書(いわゆる「離婚協議書」)は個人でも作成することは可能ですが、これを公証役場で公証人が作成したものが公正証書になります。
公正証書は公証役場で作成しますので、離婚契約を結ぶ当事者となる夫婦二人が公証役場へ行って手続を行うことが基本になります。
離婚契約の公正証書はどの公証役場でも作成できますので、利用者の側が公証役場を自由に選ぶことができます。
したがって、自宅の近くではなく職場に近い公証役場、当事者の一方側の別居先住居に近い公証役場を利用することも構いません。
一般に、強制執行となる場合も想定し、契約上で債権者となる側に近い公証役場を選ぶことになります。
また、公正証書の作成には離婚契約の内容に応じて公証人手数料の負担が生じ、その手数料は公正証書が完成した時に公証役場へ支払います。
なお、公証役場へ申し込めば、そこで直ぐに公正証書を作成されて受け取れるものと勘違いをされている方も少なくありません。
理論上はそうした対応になりますが、実務の現状としては即日の公正証書作成は原則として難しい状況にあります。※対応する公証役場が無いとは言えません、
申し込み後に公証役場における準備期間を空けることが実務として定着しており、公証役場によっても異なりますが一週間から三週間くらいの待ち期間が生じます。
また、公正証書は公文書として信用の高い証書となるため、契約する本人を確認する手続きを写真付の公的身分証明書又は印鑑証明書で行うことになります。
第三者が本人に成りすまして公正証書を作成できない仕組みになっています。
離婚の届出前における離婚公正証書を作成するときは、養育費などを払う契約の前提として離婚する合意も契約に含まれるため、原則としては本人二人が公証役場へ出向くことになります。
結婚又は離婚という重要な身分に関する意思の確認を伴う手続きは、通常は代理人で行わないことから、本人が手続きすることが原則となることは理解できます。
仮に、何かしらの手違いが生じて本人の意思に反して身分の変更に関する公正証書が作成されたならば、そのあとに修正する手続は容易ではありません。
ただし、本人が公証役場に出向くことができない事情があるときは、公証人が認めるならば、本人が代理人を指定し、その代理人が公証役場へ代わりに出向いて手続きすることもあります。
どうしても本人で対応できない事情を持つ方もありますので、個別の事情を踏まえて代理人による公正証書の作成を公証人も認めることがあります。
ただし、原則として代理人による離婚公正証書の作成を認めない公証役場も多くありますので、代理人による対応をとるときは注意が要ります。
なお、夫婦の一方が他方の代理人を兼ねることはできませんので、配偶者ではなく、本人の親・兄弟姉妹、弁護士、行政書士などを代理人に指定することになります。
契約する当事者が公証役場へ出向くことで公正証書を作成します。
公証役場は国の役所になりますので、離婚に際して公正証書を作成するためには、平日の開庁している時間内に公証役場へ出向かなければなりません。
公正証書を作成するうえでネックになるのが、平日に公証役場へ行く時間の調整になります。
夫婦とも仕事についていると、双方に都合がよい日時を調整する必要があります。
しかし、公正証書を作成する時期が双方の仕事が忙しい時期に重なってしまうと、調整のつく日が申し込み日から一か月以上も先になることもあります。
夫婦で調整した日程が出てくると、その日程で公証役場側と公正証書の作成日時を調整して、公正証書を作成する日を事前に定めておきます。
なお、公証役場で予約をとった日時は、余程やむを得ない事情が生じた場合のほかは、変更しないように気を付けましょう。
いったん決定した日時を安易に変更することになれば、あらためて当事者となる二人と公証人で日程を調整しなければならず、公正証書を完成させて離婚の届出を行う日程も先へ延びてしまうことになります。
また、日程を延ばしてしまうことで、それまでに二人の一方が翻意し、他方に対し公正証書にする契約の条件を大幅に変更することを求めたり、公正証書を作成すること自体を拒む事態も起こる可能性があります。
公正証書 離婚の手続きが完了すれば、その後に市区町村役所で離婚の届出をして、それが受理されることで協議離婚が成立し、同時に離婚契約の効力が発生します。
公正証書の完成から離婚の届出までは、あまり余計な期間を空けないことも大切なことです。
離婚の届出をしない限り離婚は成立しませんから、稀な事例ではありますが、離婚の届出までに夫婦の一方側が離婚する意思を撤回する事態も起きます。
そうなると、離婚の成立を前提とした契約条件は効力が生じないことになります。
そうした離婚が成立しなくなるリスクもあるため、離婚契約の公正証書を完成させたら、そのまま役所へ出向いて離婚の届出を済ませる夫婦が多くあります。
夫婦二人で公証役場へ出向けば、その後に市区町村役所に離婚の届出をすることもできます。
また、夫婦の一方が離婚届不受理申出をしていることも少なくありません。こうしたときは、申出人が不受理申出を取り下げなければ、離婚届出をしても受理されません。
そうした事態にも対応できるよう夫婦二人で離婚の届出へ行くことは、協議離婚の成立を双方で確認することもできて、お互いに安心です。
公証役場で公正証書の原本に夫婦双方で署名と押印をする手続は、たいした時間もかからずに終わります。
事前に公証役場へ申し込みをするため、公正証書の作成日には準備して出来上がっている公正証書を夫婦で最終確認するだけになり、お互いに話し合う必要もありません。
公正証書を確認する手続は僅かな時間(15分から30分程度)で済みますので、わざわざ代理人を指定して面倒な手続を行うまでもありません。
また、通常は起きませんが、代理人による契約では、当日になって相手本人の気持ちが変ってしまって公正証書に定める条件を一部変更することになれば、代理人では判断できずその日は公正証書を作成できなくなります。
また、強制執行できる公正証書を作成する場合には、公証役場で同時に送達(強制執行の準備手続きの一つになります)を済ませることができます。
しかし、この手続きは債務者本人が公証役場に来ないと行なうことができませんので、債権者の側には都合がよくありません。
離婚を決めた後に別居を開始しているときは、相手と顔を合わせることも嫌になってしまい、公証役場に行きたくないとの話も聞くことがあります。
しかし、離婚に向けた最後の大事な手続きになりますので、公証役場で待ち合わせ、少しの時間だけ辛抱し、夫婦二人で公正証書の手続を済ませることをお勧めします。
離婚した後に公正証書契約をする場合、一方(主に金銭の支払い義務者)側が公正証書の作成に反対し、公証役場へ行きたくないと言い出す事態も起きます。
そうなってしまうと、公正証書による離婚契約を締結することは困難となります。
ただし、離婚の届出前であるときは、公正証書契約を結ぶことを離婚する条件の一つとすることで公正証書 離婚も可能になります。
実際に、はじめは公正証書離婚の手続きを嫌がっていた相手が、協議離婚する条件に加えることで、公正証書の作成に協力する姿勢を見せることもあります。
協議離婚を成立させることができないときは家庭裁判所の調整にすすみますが、家庭裁判所で離婚が決まるときには、そこで離婚条件も含めた調書が作成されることになるからです。
そうであるならば、協力して公正証書離婚をした方が早く離婚できることになります。
安心の相談、チェック対応
公正証書とする離婚契約案の作成・修正・チェックから、公証役場への公正証書の作成依頼・調整までを、離婚専門の行政書士が、あなたを丁寧にサポートさせていただきます。
サポート期間中は離婚の条件に関してのご相談にも対応させていただきます。お分かりにならないことは、いつでもご確認いただくことができます。
離婚公正証書サポートのご利用につきましては、フォーム・お電話でお問い合わせください。
離婚公正証書の作成サポートプラン
|
公正証書の作成フルサポート (3か月間の安心サポート保証付) |
5万7000円(消費税込み) |
|---|
|
契約原案の作成のみ (1か月間の安心サポート保証付) |
3万4000円(消費税込み) |
|---|
- 上記料金のほか、公証役場へ納める公証人手数料(3~8万)が必要になります。公証人手数料は、離婚契約の内容によって公証役場で算出します。
【フルサポートの内容】
- 協議離婚の条件に関しての説明、ご相談
- 公正証書の原案作成
- 原案の修正・調整
- 公証役場への申し込み(提出書類の確認、代理取得等も含みます)
- 公証人との調整
- 公正証書案のチェック、修正
【原案作成の内容】
上記の1~3までの業務がサポート対象となります。
「夫婦のどちらか一方が公証役場へ行けば、そこで公正証書を作成できる」は、明らかに間違いであり、公正証書の作成に関する大きな誤解の一つです。
協議離婚のときに作成する公正証書は、養育費の支払いなど、離婚する夫婦間の契約を定める証書になり、契約の当事者となる二人がそろわなければ、作成できません。
これは、夫婦で署名と押印を済ませた離婚協議書が完成してあっても、それを公正証書に作成するときには、あらためて二人で契約の手続きをすることになります。
特に養育費などの支払いを約束する公正証書は、支払いの遅れなどが起きたときに裁判をしなくても債務者の財産差し押さえができる執行証書になるため、公正証書を作成することは法律上の手続きとして重要な意味があります。
そうしたことから、離婚の公正証書を作成するときには、原則は夫婦二人(代理人を指定したときは代理人)が公証役場へ出向いて手続きをすることになります。
婚姻費用、公正証書離婚、不倫の慰謝料請求、示談書などの各サポートのお問い合わせは、こちらへ
離婚協議書・公正証書、夫婦の誓約書、不倫・婚約破棄の慰謝料請求(内容証明)又は示談書のサポートをご利用したい方は、お問い合わせください。
メールまたはお電話だけによるサポートにも対応しています。
なお、慰謝料請求の可否・金額評価、法律手続の説明、アドバイスを求めるお電話は、サポート契約者様との連絡に支障となりますので、ご遠慮ねがいます。

『あなたに必要な公正証書、離婚協議書、示談書等を迅速・丁寧に作成します。』
こちらは「船橋つかだ行政書士事務所」の電話番号です。
047-407-0991